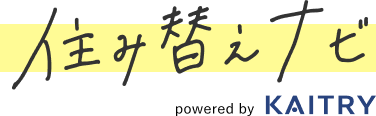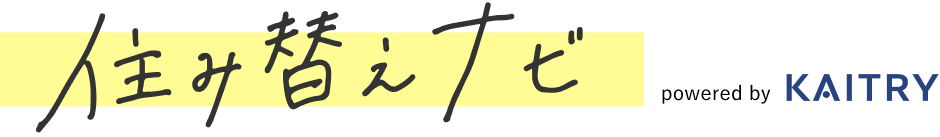マンションを相続!どんな手続きが必要なの?

親のマンションを将来相続する予定の方の中には、「相続手続きは何をすればいいのか?」「自分だけで手続きできるのか?」と悩んでいる方も多いでしょう。
本記事では、マンションを相続する際に必要な手続きの流れを解説し、不安を感じたときに相談できる窓口についても紹介します。
相続税の申告手続き
相続が発生すると、相続税の申告手続きが必要になります。その手続きの概要についてご説明します。
遺言書の確認
相続が発生した際、遺言書があるかどうかを確認します。
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。自筆証書遺言は、被相続人(亡くなった方)が生前に自ら作成し保管するもので、公正証書遺言は公証役場で証人の立会いの下で作成されるものです。
いずれも法的拘束力を有していますが、自筆証書遺言は、内容の改ざんや破棄を防ぐため、開封に際して、家庭裁判所での検認手続き※が必要になる点には注意が必要です。
※検認手続き
家庭裁判所に検認手続きの申立後、期日に家庭裁判所に、相続人が会して内容確認を行います。その後、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されてから、遺言書として有効となります。なお、2020年7月10日から自筆証書遺言書保管制度(法務局に自筆証書遺言を預かってもらう制度)がスタートしており、この制度を利用する場合は家庭裁判所の検認手続きは不要となります。
相続人と相続財産の確認
被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得して、相続人の確定を行います。
また、同時に被相続人が所有している財産を確認して、相続財産の把握をします。資産の種類によっては、非課税枠が設定されていたり、評価方法が決められていたりするものもありますので、個々の相続財産の評価額を算出して相続財産の総額を求めます。
相続税の申告
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。
遺言がある場合には、その内容に従って遺産分割を行うのが原則です。
ただし、相続人全員が遺言書の内容と異なる遺産分割に同意する場合には、その限りではありません。
遺言書がない場合には、相続人の間で話し合いを行い、遺産分割の内容を決定し、遺産分割協議書を作成します。その内容に従い、相続発生から10カ月以内に、相続税を計算した上で申告および納付を行います。
関連記事はこちら
▶︎マンション相続したら、相続税はいくらかかるの?
不動産の名義変更手続き
相続財産にマンションなどの不動産が含まれる場合には、不動産の名義変更手続きが必要となります。
相続に伴う名義変更
相続に伴う不動産の名義変更の手続きは、不動産登記簿の所有権移転登記を指しており、法務局で行います。
登記申請書に必要書類を添付して、登録免許税を納付して手続きを行います。
なお、相続に伴う所有権移転登記に必要な書類は、登録免許税の計算に必要な固定資産税評価証明書のほか、遺言書の有無によって以下のような書類が必要になります。
【遺言書があり、その内容に従い相続したとき】
・戸籍謄本
被相続人の死亡時の戸籍と、相続人(不動産を相続する者)の現在の戸籍
被相続人と相続人の関係がわかる戸籍
・相続人(不動産を相続する者)の住民票または戸籍附票
・被相続人の除票または戸籍附票
・遺言書
法務局で保管されていない自筆証書遺言の場合には、検認済証明書が必要
【遺言書がなく遺産分割協議により相続したとき】
・戸籍謄本
被相続人の死亡時の戸籍と、相続人全員(・・)の現在の戸籍
被相続人と相続人全員(・・)の関係がわかる戸籍
・相続人(不動産を相続する者)の住民票または戸籍附票
・被相続人の除票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
関連記事はこちら
▶︎マンション相続時の名義変更はどうするべき?基本知識と失敗しない方法を解説
名義変更の際の注意点
相続時の所有権移転登記は、かつては義務ではありませんでした。
そのため、所有権移転登記が行われていない場合もあり、不動産登記簿上の名義人が被相続人の何代も前の親族のままになっているというケースが多くみられました。しかし、2024年4月からは義務化され、相続開始から3年以内に所有権移転登記が義務となりました。
名義変更をしようと思っても、改めて多数の相続人に該当する方と全員で遺産分割協議をする必要があります。
そのための連絡調整だけでなく、さまざまな書類をそろえる必要があり、協議には多大な労力を要します。
不動産登記簿上の名義人を変更しなくても、そのまま親族が居住するなどの利用だけであれば問題ありません。
しかし、売却や融資を受けるための担保提示には、本来の名義人と不動産登記簿上の名義人が一致している必要があり、実行に移せない可能性があります。
相続が発生してから、その状況を知って慌てることがないように、相続予定の不動産について不動産登記簿上の名義人を確認しておくことが望ましいでしょう。
手続きについての相談窓口
マンションをはじめとして、相続に伴う手続きは、すでに触れた通りさまざまなものがあります。その全てを一人で行うことに不安がある場合には、専門家に相談するのも一案です。それぞれの手続きの相談窓口をご紹介します。
相続税の申告手続き
相続税の申告手続きは、「遺産分割」の段階と「相続税の申告」の段階によって相談先が異なります。
遺産分割について
遺産分割の相談といっても、基本的な考え方を相談したい場合と、相続人の間で話し合いがまとまらず相談したい場合とに分かれます。
基本的な考え方を相談したい場合には弁護士のみならず、行政書士や司法書士、ファイナンシャルプランナーなどに相談することもできます。
ただし、相続人の間で話し合いがまとまらない場合には、最終的に調停や訴訟に発展する可能性もあるため弁護士に相談されるとよいでしょう。
相続が発生してからでは対策も限られてしまうため、あらかじめ相続問題に強い専門家に相談をしておくと、事前対策を講じる時間を持つことができます。
相続税の申告について
相続税の申告について書式等の簡易的な質問であれば、税務署で相談に乗ってもらえます。
また、マンションなどの不動産を売却してその収益を遺産分割することも視野に入れている場合には、不動産会社に査定依頼を行い、売却についての相談をしてみるとよいでしょう。
より具体的、詳細な相続税の計算、相続財産の調査や評価について相談したい場合には、税理士に相談をされるとよいでしょう。
可能であれば、相続税を専門としている税理士に相談するのが望ましいです。
名義変更手続き
マンションなど不動産の名義変更手続きについて、書式等の簡易的な質問であれば法務局で相談に乗ってもらえます。
相続人への連絡調整や添付書類の収集なども依頼を検討する際には、司法書士に相談するとよいでしょう。
まとめ
相続手続きと一口にいっても、遺言書の確認や遺産分割協議、相続税の計算および申告納付、不動産の名義人変更など、多岐にわたります。
相続税の申告期限は相続発生から10カ月と決められています。
特に仕事を持っている人にとっては、相続手続きにあてる時間も限られますので、10カ月という期間は長いようで、あっという間に期限が到来するものです。
相続が発生してから慌ただしく手続きに取りかかると、誤った判断を下しかねません。
あらかじめ専門家に相談をしておき、いざというときにスムーズに動ける準備をしておきましょう。

氏
不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルテーション、CREコンサルティングなどを行うかたわら、同分野の連載を月15本、テレビ、ラジオのレギュラー番組への出演 多数。
また全国新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演を毎年多数。
HP
https://www.yoshizakiseiji.com/
著書
間違いだらけの住まい選び
「不動産サイクル理論」で読み解く 不動産投資のプロフェッショナル戦術
データで読み解く賃貸住宅経営の極意
大激変 2020年の住宅・不動産市場
「消費マンション」を買う人 「資産マンション」を選べる人
など全12冊、他連載多数